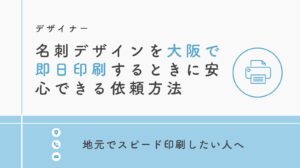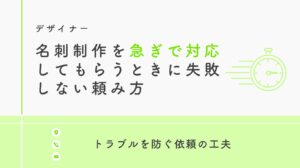子ども 夜中 熱 受診目安を知り不安な夜も落ち着いて対応する方法
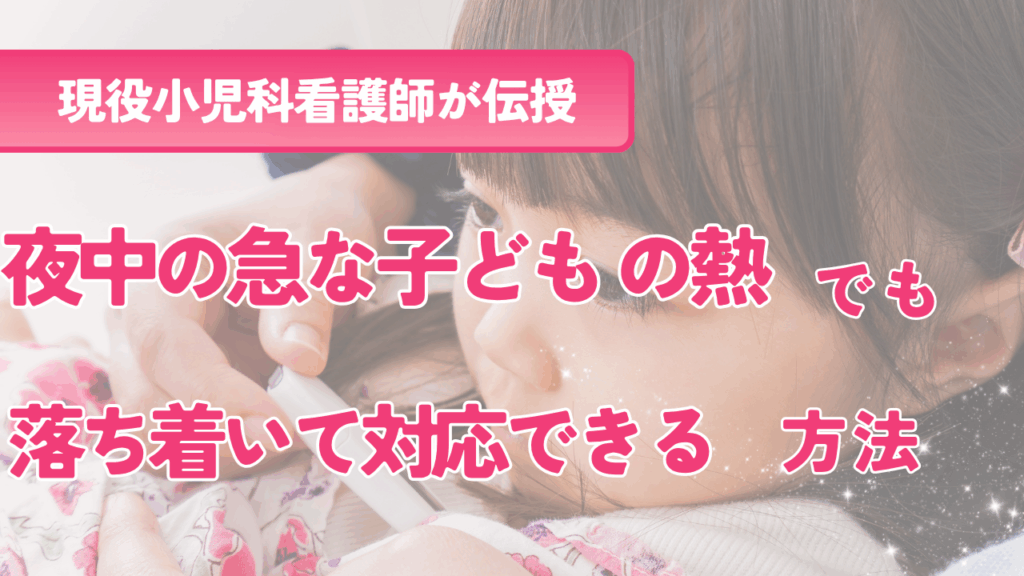

夜中、子どもの体が熱くなっていることに気づいた瞬間。時計を見れば深夜、病院も閉まっている…。
そんな時、ママやパパは不安でいっぱいになりますよね。
「救急に行くべき?」「朝まで様子を見ていいの?」と、迷うのは自然なことです。
でも大丈夫。
慌てずに“確認すべきポイント”を押さえることで、落ち着いて行動できます。
この記事では、夜中に子どもが熱を出したときの【受診目安】や【自宅でのケア方法】をわかりやすく解説します。正しい知識を持つことで、不安な夜を少しでも安心に変えていきましょう。
子どもが夜中に熱を出したとき親が最初に確認すべきこと
夜中に熱を出したとき、まず大切なのは「冷静に観察すること」です。焦って体温計を何度も当てたり、すぐに解熱剤を使ったりする前に、子どもの“全体の様子”を見てください。元気に泣いたり話したりできるか、顔色や呼吸の様子はどうかをチェックします。熱の高さだけでは病気の重さは判断できません。しっかり観察し、落ち着いて行動することが、子どもを守る第一歩です。
体温の測り方と測定する最適なタイミング
体温は測る場所やタイミングで変わります。脇で測る場合は汗をふき、肌に密着させて測定します。
大人用の体温計で大丈夫。体温計の先端が脇の中心に当たるように測定すると正確です。
測定は食後や入浴直後を避け、安静にしているときに行いましょう。
熱があるかどうかを何度も測る必要はありません。むしろ測りすぎると誤差が出やすく、不安も増します。
おおまかに「今より上がりそうか」「下がってきたか」を知る程度で十分です。
左右の差がある時は高い方を採用してくださいね。
熱以外の症状(呼吸・意識・水分摂取)の観察方法
熱そのものよりも、呼吸の速さや息苦しさ、反応の鈍さ、水分が取れているかが重要です。
苦しそうに息をしていたり、呼びかけに反応しない、ぐったりしている場合は要注意。
口の中が乾いていたり、尿の回数が極端に減っている時も脱水のサインです。
明らかに普段と違うと感じたら、迷わず医療機関へ相談しましょう。
受診が必要な目安を知ることで不安を減らす
「どのくらいの熱で受診すればいいのか」は、多くの保護者が悩むポイントです。
基本的には、熱の高さよりも“子どもの様子”を見て判断します。
ぐったりしていない、笑顔が見られる、しっかり水分が取れていれば急を要することは少ないです。
とはいえ、特に乳児や持病がある子どもは注意が必要。
年齢や症状によって「すぐ受診」「翌朝でOK」の見極め方を知っておくと安心です。
すぐに受診すべき高リスクの症状
生後3か月未満の発熱、意識がもうろうとしている、けいれん、息苦しさ、顔色の悪さ、繰り返す嘔吐などが見られる場合は、夜間でも迷わず受診を。これらは重症化のサインであることがあります。
救急外来を受診する際は、症状の経過や体温の変化をメモしておくと診察がスムーズです。
翌朝まで様子を見ても良いケースの判断基準
元気があり、水分も取れている、発熱以外の症状が軽い場合は、夜間救急に行かず朝まで様子を見ても大丈夫です。
夜間に無理して受診すると、子どもに負担がかかることもありますし、他の感染症に感染するリスクにも。
心配な時は「#8000(子ども医療でんわ相談)」で専門家にアドバイスをもらいましょう。
救急相談窓口の活用方法
「#8000(子ども医療でんわ相談)」は全国どこからでも利用できる便利な窓口です。
看護協会の専門研修を受けた看護師や夜間の対応についてアドバイスしてくれます。
地域によってはLINE相談が使える自治体もあります。
受診の必要性を冷静に判断するためにも、まずは電話相談を活用しましょう。
夜中に落ち着いて行動するための準備リスト
いざという時に慌てないために、お薬手帳・母子手帳・健康保険証・診察券をひとまとめにしておきましょう。
夜中に灯りをつけて探すのは意外と大変です。さらに救急病院の場所や電話番号も事前に確認を。
準備しておくだけで、いざという時の安心感が大きく変わります。
自宅で様子をみれる場合、体重に合った解熱剤があれば安心です。
坐薬(アセトアミノフェン坐剤)であれば、体重10kg➡️100mg 20kg➡️200mgが適量です。
冷蔵庫に常備しておく事に加えて、子どもに体重に適正量か?を知っておくと安心です。
自宅でできる子どもの発熱ケアの方法
受診までの間、自宅でできるケアはとても大切です。熱は体がウイルスと戦っているサイン。
無理に下げようとせず、子どもが快適に過ごせるよう整えてあげましょう。
こまめな水分補給、室温や服装の調整、眠れる環境づくりが基本です。
水分補給と快適な室温管理
水分不足は熱のランクを上げてしまいます。こまめな水分補給が大切です。お茶や水・好きなジュースでもOK、少しずつ与えましょう。室温は20〜25℃を目安に、加湿も忘れずに。
厚着をさせると熱がこもりやすくなるため、薄手のパジャマにしましょう。
解熱剤を使用する際の注意点と最適なタイミング
解熱剤は「つらそうな時」に使うのが基本です。数字だけで判断せず、眠れない・ぐったりしている場合に使用します。
目的(水分を摂らせる・夜間の睡眠確保・頭痛などの痛みの緩和)を持って使用すること。
座薬を入れた後は、30分ほどして汗をかき始めたら着替えを。
薬を使っても一時的に下がるだけなので、無理に繰り返し使用しないようにしましょう。
また、時には解熱効果が感じられないこともありますが、子どもが少しでも楽になり、目的が達成されているようなら様子みてもOKです。解熱剤を使用しても下がらないことはよくあります。
信頼できる医療情報サイトや相談窓口
「日本小児科学会」「厚生労働省」「教えてドクター」などの公式サイトには、子どもの発熱に関する信頼できる情報が掲載されています。SNSの体験談だけを頼りにせず、根拠ある情報をもとに行動しましょう。
親が落ち着いて対応することで子どもに与える安心感
子どもは親の表情や声のトーンを敏感に感じ取ります。親が落ち着いていると、子どもも安心します。不安な夜こそ、深呼吸して「大丈夫」と声をかけてあげましょう。知識を持つことで、自然と心にも余裕が生まれます。
親の心構えとストレス軽減の工夫
子どもの発熱は誰にでも起こること。一説には、子どもは年間12回熱を出します。
決して寒かったからでも、食べ物が悪かったからでもありません。
自分を責めずに、できることを一つずつ行いましょう。
パートナーと役割を分担したり、家族や友人に話を聞いてもらうのも大切です。
完璧を目指すより、「今できる最善」を意識して。
家族で共有しておきたい発熱対応マニュアル
家族全員が対応方法を知っておくと、誰かが不在でも安心です。
解熱剤の場所、病院への行き方、相談窓口の番号などを一覧にまとめておきましょう。
共有することで「不安な夜」を「乗り越えられる夜」に変えられます。
🩷まとめ
夜中の発熱は、どんな家庭にも起こりうることです。
「知っているかどうか」で、親の不安も子どもの安心も大きく変わります。
今回ご紹介したポイントを押さえれば、夜間でも落ち着いて判断・対応できるようになります。
大切なのは、“慌てず観察し、必要なときに適切な行動をとること”。
親の冷静さが、子どもにとって何よりの安心です。
正しい知識を備えて、どんな夜も少しずつ「大丈夫」と思える自信をつけていきましょう。
不安なあなたにおすすめの講座
『子どもお家ケアスペシャリスト講座』
2時間の講座で、子どもの急病時に必要な判断と行動がわかる講座。
投稿者プロフィール

- 小児医療アドバイザー講師/看護師/HOIKU to CARE代表
- 発熱・ケガ・肌トラブルなど、保育や家庭でよくある「ちょっと困った」に対応できる力を育む講座を展開中。小児科看護師歴28年、1万人以上の親子と関わった経験を活かし、専門的すぎない、でも根拠のある医療知識を届けている。三姉妹の母としての実体験も講座に反映。
最新の投稿
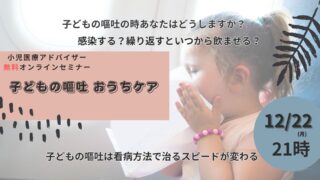 子育て・教育を学ぶセミナー2025年12月15日📢 小児医療アドバイザー無料オンラインセミナー
子育て・教育を学ぶセミナー2025年12月15日📢 小児医療アドバイザー無料オンラインセミナー 活動日記2025年11月28日知っててよかった!赤ちゃんの肌とアレルギー予防の話
活動日記2025年11月28日知っててよかった!赤ちゃんの肌とアレルギー予防の話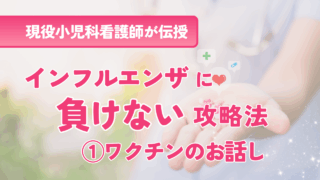 子育て・健康(子ども)2025年10月21日子どものインフルエンザ予防はいつから?ワクチンの効果・フルミストとの違いをわかりやすく解説
子育て・健康(子ども)2025年10月21日子どものインフルエンザ予防はいつから?ワクチンの効果・フルミストとの違いをわかりやすく解説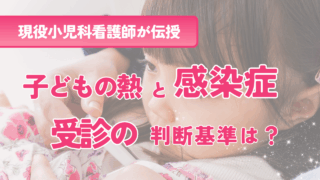 子育て・健康(子ども)2025年10月20日子どもの熱が続いた時、感染症を疑う判断基準は?
子育て・健康(子ども)2025年10月20日子どもの熱が続いた時、感染症を疑う判断基準は?