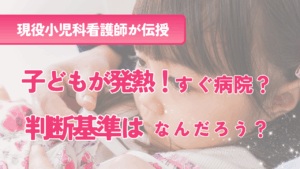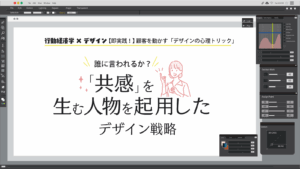子どもの熱が続いた時、感染症を疑う判断基準は?


子どもの熱がなかなか下がらないとき、「これって長引きすぎ?」「いつ病院に行くべき?」
と不安になることはありませんか。発熱は体がウイルスや細菌と戦っているサインですが、
続くと心配になりますよね。特に、数日経っても熱が下がらない場合は「重大な病気かも…」と不安が募ります。
でも大丈夫。子どもの発熱は、多くの場合、体の防御反応として自然に起こるものです。
大切なのは、どんな症状のときに受診すべきか、どんな時は自宅で見守っていいかを知っておくこと。この記事では、熱が下がらない原因や受診のタイミング、自宅ケアのポイントをやさしく解説します。
子どもの熱が下がらないときに知っておきたい基本の考え方
発熱は「体が外敵をやっつけようとしている証拠」。つまり、すぐに悪いことではありません。
熱が出ると不安になりますが、焦って解熱剤を使うよりも、まずは“熱が出る理由”を理解しておくことが大切です。発熱が長引くときは、その背景にある原因を冷静に見極めましょう。
発熱のしくみと「熱が出ること」の意味
体がウイルスや細菌に感染すると、免疫が働いて体温を上げます。これは病原体を倒すための防御反応です。
つまり「熱=悪」ではなく、「体が頑張っているサイン」。無理に下げると回復が遅れることもあります。
あくまで、自分で上げている熱なので、自分が耐えられないような事態になることはありません。
どのくらい続くと「下がらない」と判断すべきかの目安
一般的には、4日以上高熱(38.5度以上)が続く場合は注意が必要です。
軽い風邪なら2〜3日で下がることが多いですが、4日以上続くときや、日ごとに悪化する場合は医療機関に相談しましょう。
子どもの熱が下がらない主な原因とは
熱が長引く原因には、大きく分けて「ウイルス感染」と「細菌感染」があります。
子どもが重症化しやすいのは【細菌感染】、だから生後2ヶ月から開始の乳児ワクチンは
この【細菌感染】予防のヒブ(現在は五種混合ワクチンに入っている)と肺炎球菌ワクチンがある。
ウイルスによる発熱は多くが自然に治まりますが、細菌感染は抗生物質などの治療が必要です。
また、免疫の異常や慢性炎症が隠れている場合もあるため、経過観察が大切です。
ウイルス感染による一時的な発熱
風邪やインフルエンザなどのウイルス感染では、2〜3日ほど高熱が続くことがあります。ウイルスは時間とともに体が処理するため、多くの場合は自然に解熱します。
細菌感染や炎症性疾患など、受診が必要なケース
肺炎、中耳炎、尿路感染症などの細菌感染は、熱が長引くサインです。そして大半が他の症状が強かったり、ぐったり感が強かったりします。ウイルス感染とは違い、抗生剤治療が必要になります。
呼吸が苦しい、尿の色が濃い、耳を痛がるなどの症状がある場合は早めに受診を。
繰り返す発熱に隠れている病気の可能性
数週間にわたって発熱を繰り返す場合、PFAPA症候群や自己免疫性疾患など、特殊な病気が関係していることもあります。定期的に熱が出るようなら小児科で相談を。受診時には、必ず詳細な記録をしていきましょう。
カレンダーに記録することもおすすめです!
受診のタイミングを見極めるための判断ポイント
「何日続いたら受診?」という明確な線引きはありませんが、するとすれば丸3日です。中には普通の風邪でも7日間続くことも、医療現場では比較的見かけます。
だから、熱の日数や高さよりも、子どもの“様子”が最も重要です。元気がない、食欲がない、呼吸が速いなどは受診のサイン。
逆に、笑顔があり水分を取れていれば急を要しません。
何日も熱が続くときにチェックすべき症状
発疹、咳、下痢、嘔吐、尿の減少などが続く場合は注意。これらは感染症の合併症や脱水のサインであることがあります。
ぐったり・水分がとれない・呼吸が苦しそうなときはすぐ受診
顔色が悪い、唇の色がいつもと違う、息が荒い、意識がもうろうとしているなどは緊急受診が必要。夜間や休日でもためらわず救急外来を利用しましょう。
受診の前にまとめておくと良い観察メモ
体温の変化(朝昼夜の3回測定)、熱以外の症状、飲食量、睡眠、排尿の回数をメモしておくと診察がスムーズです。
自宅でできる熱のケアと過ごし方のコツ
高熱でも、本人が元気であれば慌てる必要はありません。例え40度でも元気な子もいます。
自宅で快適に過ごせる環境を整えましょう。判断の軸は子どもの様子です。
熱が下がらないときの正しい水分補給と休ませ方
水分不足は、熱のランクを上げてしまいます。+1℃になることも。
こまめに水分を与え、脱水を防ぎます。経口補水液や麦茶、スープなどを少しずつ。量は少なく回数多くを意識しましょう。
無理に食べさせず、大人が快適と思う環境でOK。
解熱剤を使うタイミングと注意点
解熱剤は「つらそうなとき」に目的を持って使うのが基本。熱でしんどそうなで眠れない時。
熱でぐったりして水分を取ってくれない時。頭痛などの痛みの強い時。眠らせる・飲ませるなどの目的の為に使いましょう。
解熱剤の効果は4〜6時間。薬効が切れると再上昇します。急激な熱のアップダウンは体力を消耗します。
連続使用は避け、医師の指示を守りましょう。また、解熱剤を使っても解熱しないこともよくあります。
でも、痛みや辛さを取ってくれたのなら、目的は達成です。
睡眠・食事・服装の調整で体の回復をサポート
厚着をさせず、通気性の良い服で。冷やしすぎは逆効果です。食事は消化のよい炭水化物(米・うどん・芋類など)がおすすめ。
避ける食事は、脂肪分の多いもの(揚げ物・高脂肪の乳製品など)は避けましょう。
本人の嗜好に合わせて、食べられるものを少量ずつこまめに与えましょう。
夜間や休日に熱が続くときの対応方法
夜間や休日は病院が閉まっており、不安が募りますよね。そんなときこそ「落ち着いて観察」が大切です。
本人が、眠れている。意識の異常がない。呼吸苦もないようならゆっくり寝かせてあげてください。
夜間救急に行くか迷ったときの判断基準
元気があり、水分を取れているなら朝まで様子を見てもOK。呼吸が苦しい、ぐったりしている場合は夜間救急を利用しましょう。
電話相談窓口「#8000」の上手な活用法
全国共通の「#8000(子ども医療でんわ相談)」では、看護師や医師が対応してくれます。受診の目安を知るだけでも安心できます。
体温・症状を記録する「発熱ノート」のすすめ
体温や症状、薬の使用時間を記録しておくと、医師に伝えやすくなります。また、続けて記録することで病歴の確認や発熱頻度の確認もでき総合的な判断に有効です。
家族で共有しておきたい受診先と緊急連絡先
かかりつけ医、夜間救急、#8000などを家族で共有しておくと、いざという時に安心です。
また、急な熱などで慌てないよう協力を依頼できる方(祖父母や親の兄弟、近所の方)とのコミュニケーションを測っておきましょう。
親が落ち着いて行動するためのメンタルケア
看病中は眠れない夜が続きます。深呼吸をして、短時間でも休息を。完璧を目指さず「できる範囲で」が大切です。
投稿者プロフィール

- 小児医療アドバイザー講師/看護師/HOIKU to CARE代表
- 発熱・ケガ・肌トラブルなど、保育や家庭でよくある「ちょっと困った」に対応できる力を育む講座を展開中。小児科看護師歴28年、1万人以上の親子と関わった経験を活かし、専門的すぎない、でも根拠のある医療知識を届けている。三姉妹の母としての実体験も講座に反映。
最新の投稿
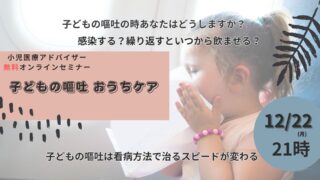 子育て・教育を学ぶセミナー2025年12月15日📢 小児医療アドバイザー無料オンラインセミナー
子育て・教育を学ぶセミナー2025年12月15日📢 小児医療アドバイザー無料オンラインセミナー 活動日記2025年11月28日知っててよかった!赤ちゃんの肌とアレルギー予防の話
活動日記2025年11月28日知っててよかった!赤ちゃんの肌とアレルギー予防の話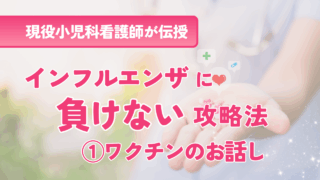 子育て・健康(子ども)2025年10月21日子どものインフルエンザ予防はいつから?ワクチンの効果・フルミストとの違いをわかりやすく解説
子育て・健康(子ども)2025年10月21日子どものインフルエンザ予防はいつから?ワクチンの効果・フルミストとの違いをわかりやすく解説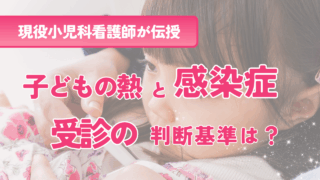 子育て・健康(子ども)2025年10月20日子どもの熱が続いた時、感染症を疑う判断基準は?
子育て・健康(子ども)2025年10月20日子どもの熱が続いた時、感染症を疑う判断基準は?