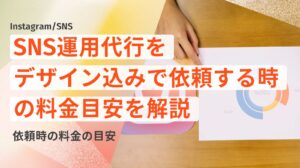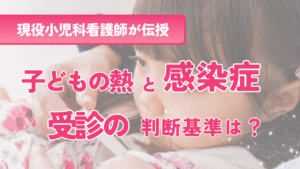子どもが発熱! 病院行く?判断基準はなんだろう?
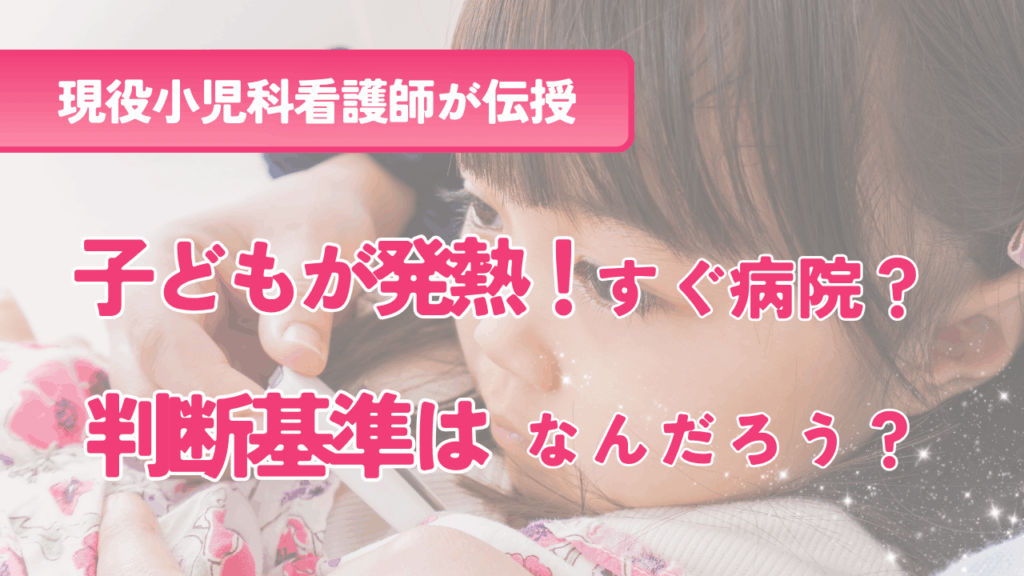

子どもが発熱したとき、「何度までなら様子を見ていいの?」「このまま夜を越えて大丈夫?」と不安になる親御さんは多いですよね。特に初めての発熱では、どう判断すれば良いか迷うものです。
でも、実は幼児の発熱はとてもよくあること。多くの場合、体がウイルスや細菌と戦っている証拠です。大切なのは、熱の高さよりも子どもの“様子”を見極めること。この記事では、受診の目安や家庭でできるケア、落ち着いて対応するための準備までをやさしく解説します。正しい知識を持つことで、「不安な夜」を「安心して見守れる時間」に変えていきましょう。
幼児の発熱はよくあること?
まず知っておきたい基本知識
幼児期は免疫がまだ未発達のため、風邪やウイルスにかかりやすく、発熱を繰り返すのは自然なことです。1歳から3歳ごろまでは、年間で5〜10回の発熱があるともいわれています。発熱は体が外敵と戦っているサインであり、すぐに「重症」と結びつける必要はありません。
ただし、発熱の原因や経過を見誤ると重症化につながることもあります。まずは「なぜ熱が出るのか」「どう体が反応しているのか」を理解しておきましょう。
そもそも発熱とは何のサイン?体の仕組みをやさしく解説
発熱とは、体がウイルスや細菌と戦うために体温を上げている状態です。体温を上げることで免疫細胞の働きを活発にし、病原体を退治しやすくしています。つまり「熱を出す=体の防御反応」。すぐに下げようとするよりも、体が回復するための自然なプロセスとして見守ることが大切です。
幼児が熱を出しやすい理由と年齢ごとの特徴
0歳児は母親からもらった免疫は
🆚細菌⇨生後2ヶ月で低下
🆚ウイルス⇨生後6ヶ月〜12ヶ月
母親からの免疫が切れる頃が風邪デビュー時期!
1〜3歳になると保育園などで集団生活が始まり、感染機会が増加。小さな体で新しい免疫をつくるため、発熱が頻繁に起こります。成長の一部と考え、焦らず見守る姿勢が大切です。1回の風邪でひとつ強くなるんです。
幼児の発熱で受診するべき体温の目安とは
「38.5度を超えたら病院?」と考える方も多いですが、熱の高さだけで判断するのは危険です。大切なのは、子どもの全体の様子。しっかり水分を取れているか、呼びかけに反応するか、いつも通り笑えるかが目安になります。体温はあくまで“目印”としてとらえ、他のサインと合わせて判断しましょう。
年齢別(0歳・1歳・3歳以上)の受診目安と注意点
- 0歳:生後3か月未満で38度以上 → すぐ受診
- 1歳:39度以上・ぐったり・機嫌が悪い → 翌朝まで待たずに相談
- 3歳以上:39.5度超でも元気なら様子見可能
ただし、呼吸が苦しそう、発疹がある、下痢や嘔吐を繰り返す場合は早めに医療機関へ。
熱の高さより大切な「子どもの元気さ」の見極め方
「笑顔がある」「おしゃべりできる」「遊びたい気持ちがある」なら大丈夫。逆に、反応が薄い、呼吸が荒い、顔色が悪いなどのサインがあるときは注意が必要です。
受診を迷ったときに確認したい危険サイン
「この症状、様子を見てもいいのかな?」と迷うときは、次のチェックポイントを意識しましょう。呼吸、意識、水分摂取の3点が基本です。ぐったりしている、呼びかけに反応が鈍い、息が苦しそう、水分が取れない、尿が減っているなどの状態があれば、夜間でも受診を。
すぐに病院へ行くべき症状(ぐったり・呼吸・水分摂取)
特に注意が必要なのは、息苦しさやけいれん、顔色の悪さが続くなど。
そして生後3か月未満の赤ちゃんの発熱は必ず受診が必要です。
症状の変化を時系列でメモしておくと、医師に伝えやすくなります。
自宅でできる幼児の発熱ケアと過ごし方
発熱中は体が戦っている最中。体温を無理に下げるより、快適に過ごせる環境づくりが大切です。
泣いて嫌がるのに冷やす必要はありません。
部屋の温度と湿度を整え、水分をこまめにとり、眠りやすい服装にしてあげましょう。
水分補給・服装・室温など快適に過ごすための工夫
汗をかいたら着替えをして清潔に。飲み物は水やお茶、経口補水液などを少しずつ。
本人が好きな飲み物があればそれでもOK!室温は22〜25度前後、湿度は50〜60%を保つと快適です。
解熱剤を使うタイミングと注意点
熱がつらそうで眠れないときや、ぐったりしているときに使用します。解熱剤はあくまで「楽にするため」であり、病気を治す薬ではないことを覚えておきましょう。水分が取れていて、眠れているようなら使用する必要はありません、急激な熱の上下は体力を奪ってしまい、病気の治癒にはマイナスの効果になることもあります。
夜間の看病で親が意識したい「見守りのコツ」
頻繁に起こさず、静かに様子を確認するのがポイント。体温や症状を時系列でメモすることで、翌朝の受診にも役立ちます。親も休息をとりながら見守りましょう。
信頼できる発熱情報サイト・ガイドラインの紹介
日本小児科学会、厚生労働省の「子どもの救急」サイトや「教えてドクター」などが参考になります。
公式情報をブックマークしておきましょう。
家族で共有したい発熱対応マニュアルと緊急連絡先リスト
家族全員が対応方法を知っておくと安心です。病院・救急・相談窓口の連絡先を一覧にまとめ、冷蔵庫などに貼っておくと便利です。地域の状況を把握する(小児救急輪番担当)。
親の落ち着きが幼児の安心につながる理由
子どもは親の表情や声のトーンを敏感に感じ取ります。親が落ち着いているだけで、子どもは安心し、回復力も高まります。「大丈夫、一緒に頑張ろう」と伝えることが、何よりのケアです。
不安を抱える親ができるメンタルケア
深呼吸をしたり、少しの間でも横になったり。看病は体力も気力も使います。完璧を目指さず、「いま自分にできること」を一つずつ。
子どもに安心感を伝える声かけと関わり方
「大丈夫だよ」「頑張ってるね」と声をかけるだけでも、子どもは安心します。抱きしめてあげること、手を握ることも立派なケアです。
まとめ
幼児の発熱は、成長の過程で誰もが通る道です。
大切なのは、体温の数字よりも子どもの“元気さ”を観察すること。
受診の目安を知り、危険サインを理解しておくことで、慌てずに行動できます。
家庭での準備や正しい情報の活用が、親の不安を大きく減らしてくれます。
親が落ち着いていることが、子どもにとって一番の安心です。
「知ること」は「守ること」。今日から少しずつ、あなたの家庭にも安心を増やしていきましょう。
投稿者プロフィール

- 小児医療アドバイザー講師/看護師/HOIKU to CARE代表
- 発熱・ケガ・肌トラブルなど、保育や家庭でよくある「ちょっと困った」に対応できる力を育む講座を展開中。小児科看護師歴28年、1万人以上の親子と関わった経験を活かし、専門的すぎない、でも根拠のある医療知識を届けている。三姉妹の母としての実体験も講座に反映。
最新の投稿
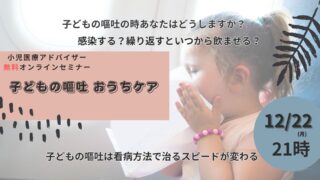 子育て・教育を学ぶセミナー2025年12月15日📢 小児医療アドバイザー無料オンラインセミナー
子育て・教育を学ぶセミナー2025年12月15日📢 小児医療アドバイザー無料オンラインセミナー 活動日記2025年11月28日知っててよかった!赤ちゃんの肌とアレルギー予防の話
活動日記2025年11月28日知っててよかった!赤ちゃんの肌とアレルギー予防の話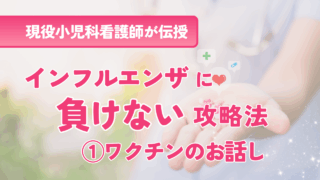 子育て・健康(子ども)2025年10月21日子どものインフルエンザ予防はいつから?ワクチンの効果・フルミストとの違いをわかりやすく解説
子育て・健康(子ども)2025年10月21日子どものインフルエンザ予防はいつから?ワクチンの効果・フルミストとの違いをわかりやすく解説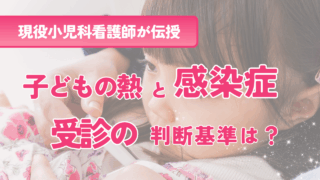 子育て・健康(子ども)2025年10月20日子どもの熱が続いた時、感染症を疑う判断基準は?
子育て・健康(子ども)2025年10月20日子どもの熱が続いた時、感染症を疑う判断基準は?